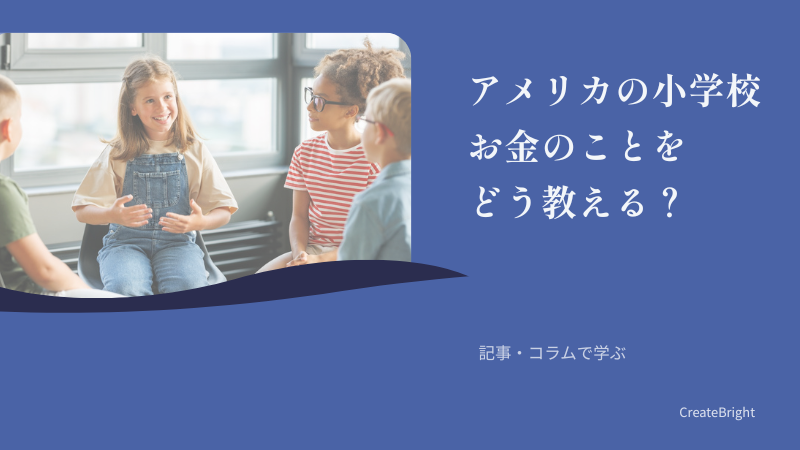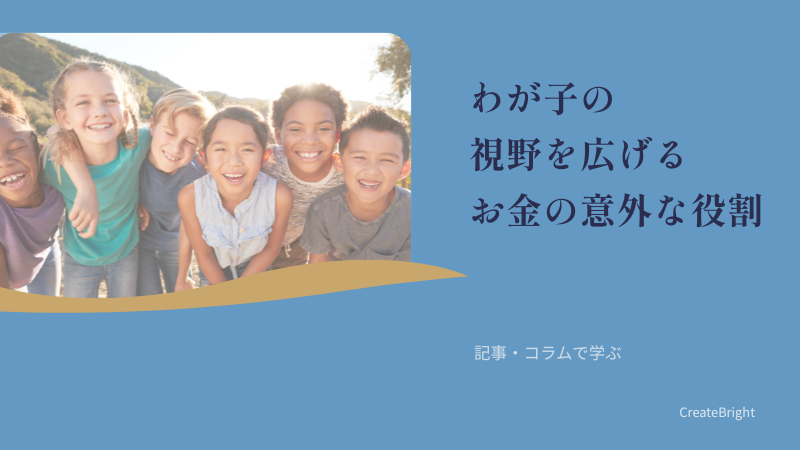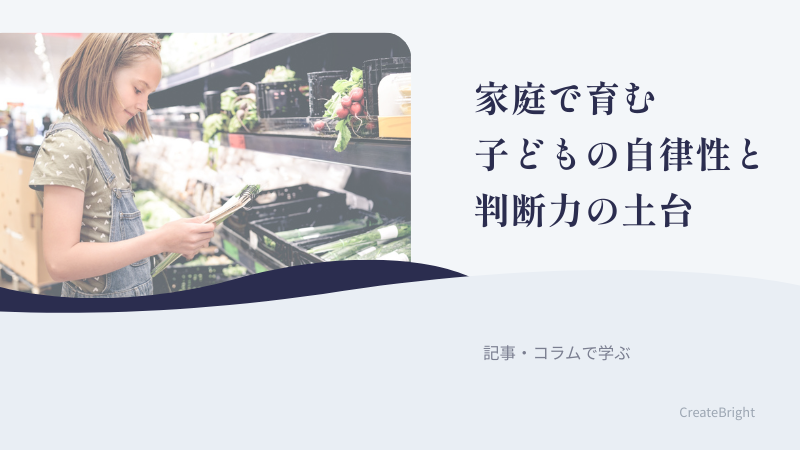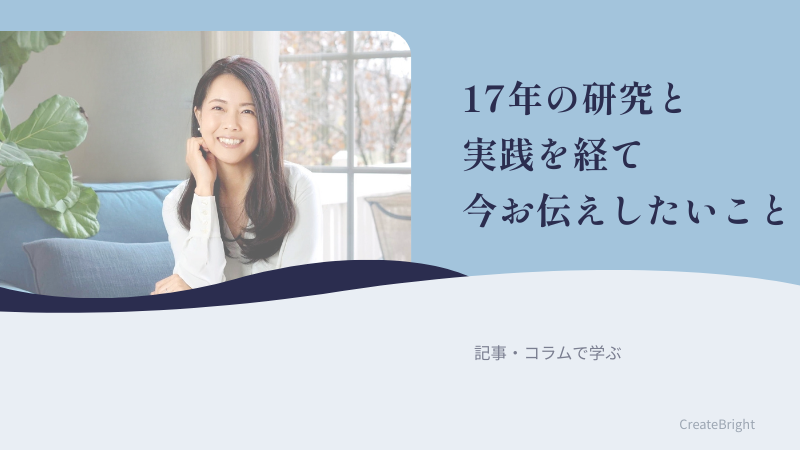【記事・コラムで学ぶ】 Page 1
18歳になる前に手渡したい、お金という名の「共通言語」
「こどもNISAのことを考えて、早く投資を教えなきゃ」 「キャッシュレス時代だから、カードの使い方やデジタル管理を教えないと」
そんな焦りにも似た金融教育の波に、少し違和感を抱いていませんか?
資産形成やリスク管理の「技術」はもちろん大切です。しかし、それ以上に大切なのは、お金の役割を正しく捉え、お金という「社会の共通言語」を使いこなし、自分らしく生きるための土台を作ることです。
「貯金さえあれば安心」という時代は終わりました。18歳という自立の門を叩く前に、お子さんに手渡したいのは、単なる「テクニック」ではなく、「人生という航路を描くための羅針盤」です。
なぜ、「増やす技術」だけでは不十分なのか
羅針盤とは、「自分のお金が、社会のどこに、どう繋がっているか」を見通す力のことです。
なぜ、単に数字を増やす技術だけでは不十分なのでしょうか。それは、自分一人だけが効率的にお金を貯めても、周りの社会が不安定であれば、その資産を守り抜くことは難しくなるからです。
景気の変動やインフレ、あるいは予測できない社会の変化。そんな荒波の中でも、自分の人生を安定させるためには、自分のお金を管理するスキルと同時に、「社会がどういう仕組みで動き、自分はどうそこに参画しているか」という視点が不可欠なのです。
「社会との繋がり(OS)」を教える教育は、たとえ手元のお金が減っても、「社会の仕組みを使って再起する力」や「他者と信頼を築いて新しい価値を生む力」を育みます。これは理想論ではなく、不確実な時代における究極の「リスクマネジメント」です。
自分のお金を大切に扱うことは、自分が生きる社会を大切に扱うこと。海外の金融教育先進国で教えられているのは、まさにこの「自分と社会を地続きに捉える」視点です。
日本とは逆だった? 海外に学ぶ「お金の教育の順番」
私が海外での生活や子育てを通じて目にしてきたのは、日本で一般的に語られているものとは全く異なる「お金の教育の順番」でした。
金融教育の先進国では、「いかに自分の資産を増やすか」という技術を学ぶ前に、まず「お金を通じて社会にどう参画するか」という市民教育としての金融教育を徹底して学びます。
特筆すべきは、その開始時期です。イギリスやオーストラリア、北欧諸国では、小学校の低学年から「社会と自分との繋がり」を学び始めます。自分のお金だけを見るのではなく、社会全体がどう回っているのかを先に理解することで、幼い頃から「社会と繋がった経済観」を養うのです。
「お金を扱うことは、社会に参加することである」
この捉え方自体を、まだお金を稼ぐ前の幼い頃から身につけていく。この土台があるからこそ、その後の資産管理の技術も、単なる蓄財ではなく、変化の激しい時代を自分らしく歩み続けるための「一生ものの基盤」へと変わるのです。
彼らが目指しているのは「自分だけが勝つための技術」ではありません。お金は単なる個人の所有物ではなく、社会をより良く動かし、同時に自分を守るための「共通言語」として位置づけられているのです。
なぜ今、日本にこの視点が必要なのか
「日本の家庭には日本のやり方がある」と思われるかもしれません。しかし、私たちがこの視点に注目すべき理由は、日本の「大人」の定義が劇的に変わったことにあります。
1.「守り」が通用しなくなった契約社会
18歳成人となった今、親のサインなしで結んだ契約の責任は全て本人に帰します。欧州で「市民としての責任」を先に教えるのは、社会という海に放り出される前に、自分自身を正しくコントロールする術を身につけさせるためです。
日本でも高校での金融教育が始まりましたが、「知識」として習うことと、実際に「自分のお金」を使って責任ある選択をすることは、全く別の体験です。18歳の誕生日に、いきなり正しい判断ができる魔法はありません。幼い頃から家庭でお金を通じた試行錯誤を積み重ねておくこと。その日常の練習こそが、本人を守るための最大の盾となります。
2.日本に足りないものを補う必要性
アメリカをはじめとする欧米諸国では、わずか5歳から、成長に合わせて、「社会の中での選択の仕組み」を、社会科(Social Studies)などの授業を通じて学びます。
私が今の日本の金融教育の波を見ていて感じるのは、この「社会と繋がる視点(経済学習)」がすっぽりと抜け落ちたまま、いきなり「どう資産を増やすか」という個人金融のテクニックに話が飛んでしまっていることへの危うさです。
土台となる社会のルールを理解しないまま技術だけを磨くのは、いわばルールを知らずにゲームのスコアの稼ぎ方だけを覚えるようなもの。だからこそ、今、以下の視点を補う必要があるのです。
北欧やイギリス、アメリカと比較して、今の日本に不足しているもの
もちろん、日本でも教育改革は進んでいます。しかし、海外の先進的な事例と比較すると、依然として以下の要素が家庭や教育現場で不足しているのが現状です。
- 早期からの体系的な教育: 「大人になってから」ではなく、幼少期から段階的に学ぶ仕組み。
- 実践的・体験型の学習機会: 知識として覚えるだけでなく、実際に使って失敗し、学ぶ場。
- 家庭でお金の話をオープンにする文化: 「はしたない」というタブーを捨て、日常の会話に載せること。
- 長期的な視点での資産形成の考え方: 目先の損得ではなく、一生を見通したリソースの管理。
これらは、単に知識を増やすだけではありません。自分自身の「お金との向き合い方」そのものを学ぶ機会です。だからこそ、学校の授業を待つのではなく、家庭での日常的な関わりが重要になってくるのです。
3.「お金=汚いもの」という呪縛を解くために
「お金の話を家庭でするのは下品だ」という古い日本的価値観。これを打破するために、「お金は社会を良くするための共通言語である」というフラットな考え方が役立ちます。損得勘定を超えて、「どう社会に参画するか」という視点を持つことで、親子で堂々とお金について対話ができるようになります。
現代における「お金の正体」:3つの新しい定義
お金=節約して貯めるもの、という常識を一度横に置いて、世界基準の金融教育が教える「今のお金」を再定義してみましょう。
- 「自由」を予約するチケット: お金の本質は、将来の自分に対する「選択肢(Choice)」です。どこに住むか、何を学ぶか。これらを自分の意志で選べる状態を支えるのがお金です。
- 「信頼」を可視化したエネルギー: お金を稼ぐとは、誰かに価値を提供し信頼を得ること。お金を使うとは、信頼できる誰かの活動を応援すること。お金は「社会を巡る信頼のエネルギー」です。
- 社会を変える「未来への一票」: 私たちが一万円をどこで使うか。その選択が、巡り巡って未来の社会構造を作ります。お金を知ることは、自分の意志を社会に反映させる具体的な方法を知ることです。
日常がそのまま「教材」に
「こんな高度なこと、家庭で教えるのは難しそう…」と感じられたかもしれません。でも、安心してください。特別な講義や難しい専門知識は不要です。
大切なのは、「教え込む」のではなく、日々の生活の中で「お金の捉え方(OS)」を少しだけ変えることです。
ご家庭での「お小遣いの渡し方」や「お買い物中の何気ない会話」。子どもたちは日常の生活の中で、この「共通言語」を自然に身につけていくことができ、積み重ねた体験によって、子どもの中の「お金の捉え方」が変わります。
大人が正解を教えるのではなく、子どもが自分自身で試行錯誤し、時には小さな失敗をしながら学んでいく。その環境を整えることこそが、家庭でできる最高の金融教育です。
自分と社会を豊かにするために、お金をどう動かすか。 これこそが、本来、義務教育の中で真っ先に学ぶべき「生きるための教養」である。私は海外での教育を目の当たりにして、そう確信しています。
しかし、制度が変わるのを待つ必要はありません。最も身近な社会である「家庭」こそが、最高の学び場になるからです。
おわりに:より良い社会を作るための「知恵」を
これまでのお金教育は、どちらかといえば「騙されない」「無駄遣いしない」といった『守り』が中心でした。しかし、これからの不確実な時代を生き抜くために本当に必要なのは、単に資産を守る技術ではなく、自らの手で人生の選択肢を広げ、自立して選び取る力です。
お金を通じて社会と健全に繋がり、自分の人生を自ら切り拓いていくための「生きた知恵(リテラシー)」を身につけること。
これこそが、CreateBrightが目指す金融教育のゴールです。