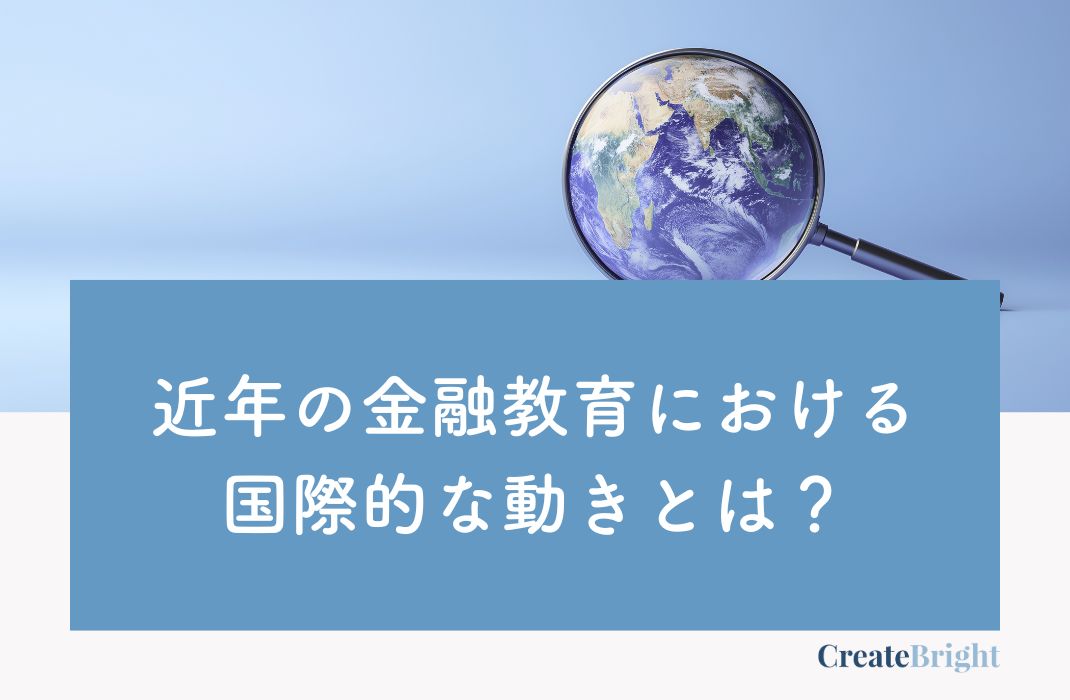堅実な日本人が苦手な、お金の使い方
堅実な日本人が苦手な、お金の使い方
日本人が得意なのは、守りの金融教育
日本でも少しずつ注目され始めた「金融教育」。
2022年から高校で始まりましたが、内容は主にローンの仕組みや資産形成の基礎知識。これらの知識は必要ですが、本当にそれだけで十分でしょうか。
日本人が得意なこと
日本人は、お金に関して以下のことが得意です。
貯金、節約、リスク管理、計画的な支出。
実際、日本の家計貯蓄率は他国と比較しても高く、堅実な家計管理ができる人が多い。これは紛れもない事実です。
私がアメリカで暮らして感じるのは、「守り」の金融教育に関して、日本人の堅実さは際立っているということ。

では、何が不足しているのか
日本の金融教育に不足しているのは、節約や貯金の知識ではありません。
不足しているのは、お金を使って自分の可能性を試す経験。
失敗を恐れずにリスクを取ってみること。うまくいかなかったら、何がダメだったのかを考えて、次に活かすこと。自分には何ができるのか、それが誰の役に立つのかを、実際に市場で試してみること。
北欧やアメリカの一部の教育現場で実践されているのは、こうした「未来を自分で切り開く力」を育てる金融教育です。
なぜ、切り開く力が必要なのか
私たち親世代が育った時代と、今の子どもたちが生きる時代は、まったく違います。
終身雇用は崩れ、年金制度は不確実になり、国や会社が生涯を保障してくれる前提はもうありません。
技術の進化は加速し、5年後、10年後にどんな仕事が必要とされるのか、誰にも予測できない。今ある職業の多くが、子どもたちが大人になる頃には形を変えているかもしれません。
だからこそ、子どもたちには「与えられた道を歩く力」だけでなく、「自分で道を創り出す力」が必要になります。
お金は、その力を育てる最良の教材です。
限られた予算の中で何を選ぶか。失敗したらどう立て直すか。自分のスキルをどう価値に変えるか。こうした判断を重ねることで、変化に対応できる力が育つ。
守りの知識も大切です。でも、それだけでは、変化の激しい時代を生き抜けない。
自分で考え、試し、失敗から学び、また挑戦する。その経験こそが、子どもたちの未来を支えます。
未来を切り開く力とは
それは、単なる楽観主義ではありません。
フィンランドの一部の学校では、6年生が模擬会社を運営します。財務管理、仕事への応募、チームワーク。全て体験を通して学ぶ。
ここで子どもたちが考えるのは:
自分のスキルが誰の役に立つのか?どうすれば価値を提供できるのか?失敗したら、何を改善すればいいのか?
こうした問いは、教室で知識を学ぶだけでは生まれません。実践を通して、試行錯誤しながら初めて自分のものになる。
スウェーデンでは小学1年生から金融教育が始まりますが、目的は単に「賢い消費者」を育てることではありません。経済的に自立し、社会に積極的に関わる力を育てること。そこを目指しているのです。
実践型学習の重要性
知識と実践は、別物です。
教室でビジネスプランの書き方を学んでも、実際に自分でやってみなければ、何も分かりません。
投資の仕組みを理解しても、実際に自分のお金を動かさなければ、感情のコントロールの難しさは分からない。
予算管理の方法を知っていても、限られたお金で何を優先するか選ぶ経験をしなければ、判断力は育たない。
北欧やイギリスの教育が重視しているのは、この「実践」なんです。
アメリカについて
アメリカは金融教育のプログラム開発では先進的。多くの州で高校までに金融教育が導入され、実践的なプログラムも豊富です。
ただし、ここで重要な事実があります。
同じ学校に通い、同じ金融教育を受けても、子どもの金融リテラシーはバラバラ。
個人負債の高さや貯蓄率の低さといった課題が指摘されているのは、学校での金融教育が充実していても、家庭での実践が伴っていない層が多いから。家庭による差が大きいのが実情です。
私はアメリカで子育てをしていて、娘たちの学校教育から学ぶことは本当に多いです。ですから、アメリカの一部の地域や家庭も、金融教育において先進しているというのは間違いでないことは実体験として証明できます。同時に、この国の経済的な課題も目の当たりにしています。
学校教育だけでは不十分。家庭での日々の実践が、子どもの金融リテラシーを左右する。
日本の家庭教育に不足しているもの
日本では、お金の話はまだまだタブー視されがち。
家庭でお金について話す機会が少ない結果、子どもが実際にお金を扱う経験が限られてしまっています。
それは意図せずとも、失敗を恐れて挑戦する機会を与えない、「小さくまとまる」ことが安全だと考えてしまうという、ことにつながっている
ということに気づいてほしいのです。
北欧やイギリス、アメリカの一部と比較すると、日本に不足しているのは、実践的・体験型の学習機会。失敗を学びに変える姿勢。そして、お金を使って可能性を広げる経験です。
CreateBrightが目指すもの
金融教育と聞いて、何をイメージしますか?子どもにどんな力をつけさせてあげたいですか?
金融教育にも色々ありますが、私たちが提供するのは、守りの金融教育ではありません。
日本の教育を受けていれば、守りはもう十分に得意です。
CreateBrightが目指すのは、実践型学習を通じて、未来を切り開く力を育てること。小さくまとまらない、可能性を広げるお金の使い方を身につけること。
これは、勝ち負けのためのお金の教育ではありません。
自分の人生を自分で選び取り、社会に積極的に関わるための教育。次世代に向けて、実践的なライフスキルをつけるための教育です。

親は、子どもにとって最も身近な大人です。だからこそ、家庭での日々の実践が、子どもの金融リテラシーを育てる上で大きな影響を持つ。
子どもの成長とともに、お金との関わり方を少しずつ広げていく。そのサポートを、これからも続けていきます。